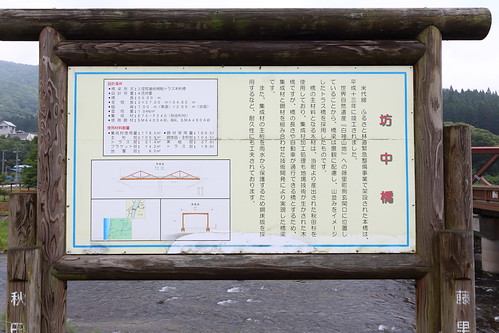|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  徳島県の恵比須浜。キャンプ場のすぐ裏は港。  そこにある大きな造船所。とても大きな扉に圧倒される。   これだけ大きな建物が、トタン板で覆われている。一部が張り替えられていて、とにかく鑑賞させられる。    これはコンクリートブロック造りのウインチ小屋。ワイヤーが出る場所のために、「顔」に見える。ウインチを操作するハンドルは、電気機関車のマスコンハンドルのようにノッチが刻まれている。レバーを握って前後に倒し、離すとそこに固定されるのだろう。ハンドル2本あるのはどうなっているのだろう。左奥のモーターから3段階で減速されるようだ。   その近くの、たぶんもう使われていない小屋。躯体の骨組みがわかる。戸が失われているので中が見える。木戸のついた物置?があるのは意外な感じがした。   陸上に引き上げられた「第十一轟丸」。「轟」が略字。コンクリートの台の上に載っているようにも見えるが、コンクリートに見える部分は海中にあって藻などが付着した部分。 PR  富山県の入善あたりから旭町にかけての海沿いは、たぶん砂丘の上に道がつけられ、海側は護岸されている。その一角に、船を引き上げる施設が並んでいる。   「鉄道」かと思いきや、レールのような位置にあるH型鋼の上に枕木方向にコロが取りつけられていて、船はコロの上を引き上げられる。  最上部にはウインチ小屋。滑車を介してワイヤーで直接船を引き上げている。このウインチ小屋は、管理者がそれぞれ工夫しているようで、すべて形が異なる。   100mほど離れたところにある「レール」はコンクリート製だ。コンクリートの「レール」の上を、鉄の車輪が動く。こちらは船を直接引き上げず、台車の上に載せる。「脱線」しないように、船を載せる台車にはガードがついている。  いや、ガードは外側だけではない。内側には案内輪がある。  ウインチで引くこと、ウインチ小屋が各自の工夫でできていることは変わらない。ワイヤーの引き方もそれぞれだが、これはワイヤー端部を最高地点に固定し、滑車を3個かませて動滑車としている。動滑車をかませば、固定している定滑車に必要な力の半分で動かせる。ウインチの出力を小さいものにするためか、それともより重い船を載せるためか。同じこの場所でも、定滑車にしているものもある。
【泊浜】
  海に向かって1車線の道を降りて行く。けっこうな斜度なので、石垣が多い。この石はどこから持ってきたのだろうか。   下り切ると、きれいな港に出る。上2枚の場所はここは東日本大震災の被害を免れたようだが、下2枚の場所は大きな被害を被ったところ。  ここにもバスは来る。牡鹿地区市民バス。 【新山浜】  【寄磯浜と寄磯小学校】  寄磯漁港。  にある、唐突な行き止まり。    物語の中の、架空の小学校かと思ってしまうような、素晴らしいロケーションの小学校。そんな能天気な印象を持ってしまうが、震災時は地域の避難所としての役割を果たした。震災当日からの記録は、公式サイトにある。現在、約100戸260人の住人に対して、児童は6人。震災前と比べ、人口は半分近くまで減ったそうだ。  寄磯中学校閉校記念碑。 【おしかホエールランド捕鯨船第16利丸】   残念ながら、2022年3月16日の地震でなにかあったのか、見学ができなかった。船体底部でも工事をしていた。 |
カレンダー
最新記事
(04/12)
(04/02)
(02/15)
(01/01)
(12/31)
(11/20)
(11/11)
(11/05)
(10/26)
(10/25)
カテゴリー
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
since 2010.7.30
アクセス解析
フリーエリア
|