|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  新潟の実家に行くたびに見ている、新潟交通入船営業所。みなとトンネルの開通と「シモ」の衰退でで役割が少し変わったが、相変わらずこの木造モルタルぽい建物が鎮座している。  相変わらず、社名や営業所名が脱落したままだ。  高校生のころは、ここにバスの定期を買いに来た。暦の月単位でしか買えなかったが、いまはどうなんだろう。  今回は何十年ぶりかで中に入ってみた。鉄道の駅ではなく、バスの営業所でこういう雰囲気があることに、たまらない魅力を感じる人は多いだろう。   朝はそれなりに通勤・通学で使う人が多いのかな。日中は閑散としていた。  バスに乗るとしたら横七番町二丁目から乗るのだけれど、この日は入船営業所から乗った。始発から乗ったのは、私含めて4人。ちょっと(?)前まで、新潟駅行きは最大でも12分に1本あったのが、いまでは土休日は1時間に2本。時刻表を見ないと乗れないものになってしまった。 また、いま「八千代橋経由新潟駅行」となっている路線は、1980年ころまでは「沼垂行」だった。また、別に「川岸町行」があった。横七番町二丁目バス停で待っていると、見えたバスの方向幕が3文字(川岸町)だと「あーあ」と思ったものだ。沼垂行は、どうやら沼垂あたりで周回してどこかで待機して新潟駅まで回送され、附船町行きになっていたようだ。新潟駅の乗り場も、右端の2番乗り場から4番乗り場に変わった。それとてあと何年だろう、高架化が完成すると、また思い出が一つ消える。 ●2012年の記事 新潟交通入船営業所 PR
・あふれこぼれる水路橋と樋曽山隧道
・新樋曽山隧道のつづき。  3本ある水路隧道の、新潟平野側から見て真ん中のものが、新々樋曽山隧道。樋曽山隧道(初代)・新樋曽山隧道は(信濃川水系の西川から引かれた)矢川の水を日本海に排出しているが、これは大通川の水を排出している。見えているのは「大通川放水路」だ。 大通川は新川の上流部分であり、人工の水路で、信濃川の水を直接排水するのではなく、潟の水を抜いて田を改良するために掘られたものだ。3本の水路隧道が並び、それぞれ日本海に排水してはいるが、この新々樋曽山隧道だけ、流す水の出自・性格が異なる。 大通川放水路はいくつかの水路と立体交差しているが、その下流である新川は西川と大規模に下立体交差している。 西川水路橋(新潟県) 水の立体交差   さて、その新々樋曽山隧道の前にはゲートがある。  隧道側から。  新新樋曽山隧道の呑み口。  隧道からゲート方向を見る。  振り返って、矢川との立体交差。水路隧道になっているのが大通川放水路。矢川は写真でいえば左右に横切っているが、当然、見えていない。  もう一度、隧道方向を。左が新新樋曽山隧道につながる大通川放水路、右が樋曽山隧道(初代)に通じる矢川の排水路。右のほうが水位がずっと高い、それは、一つ上の写真の通りに立体交差しているので、当然といえば当然だろう。
あふれこぼれる水路橋と樋曽山隧道のつづき。
 3本ある水路隧道の、新潟平野側から見て左端(南端)のものが、新樋曽山隧道。樋曽山隧道(初代)と同じく、矢川の水を日本海に排出している。   流れ込む水を制御する新樋曽山隧道水門。周囲の水田の標高が6~7mほどなので、水路の底は2~3mほどか。3門のうち右の1門は別の水路に繋がっているようだ。  反対から。  水門を抜けた水は、かなりの角度をもって新樋曽山隧道に流れ込む。  「新樋曽山隧道」という扁額が掲げられている。   近くにある新樋曽山隧道竣工記念碑。最初の樋曽山隧道からの経緯についても書いてある。文面を書いた一人は「新潟高等学校教官渡辺秀英」。 ●関連項目 新々樋曽山隧道 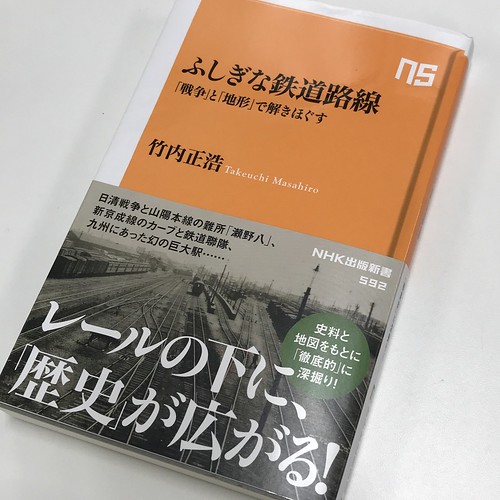 鉄道史では、しばしば日本の軍隊、特に陸軍との関わりが記述される。読む側も「そういうものか」と受け入れ、特に検証もせず、知識としている。「常識」というか「基本的な知識」というのはそういうものだろう。かくして「~といわれている」という言説が、孫引きとして繰り返される。 本書は「鉄道と日本軍は本当に関わっていた」という一次ソースを提示しつ鉄道史を解説するものだ。著者の竹内正浩氏の目的は、その一次ソースの漢文調の文書を直接読んで雰囲気を味わいつつ細かなニュアンスを掘り起こし、流れを整理する。それはもちろんおもしろいのだが、しかし、竹内氏が本書で伝えたいことは、もう一つあると感じる。それは、「明治時代から太平洋戦争の時代までの、外敵への恐怖感」、それも「高速移動手段がなかった時代の人間の感覚」を、現代人にわかってほしいということではないか。また、「何か(輸送手段の規格など)を決めるとき、軍隊の規模を基準とするという感覚」「鉄道は兵器であるという感覚」も。いずれもみな知識としては知っているだろうし、いわれれば「そうだろうな」とは思うものだが、間違いなく現代の私たちには「実感」はない。 現代の私たちは、日本の国土は自衛隊と米軍により強固に守られていると思っている、と私は思っている。何かあっても自衛隊と米軍が守ってくれそうだ。自分が避難しなければならないときは、クルマもバイクもある。新幹線が動いていれば、2時間あれば300km向こうに移動できる。しかし、鉄道もクルマも一切ない、徒歩と海路(しかも蒸気船)だけが頼りの時代だったら? 私たちが過去の何かを想像するときの基準を、本書は与えてくれる。 * * *
目次を公式サイトから転載する。 第一章 西南戦争と両京幹線 なぜ中山道ではなく東海道だったか 第二章 海岸線問題と奥羽の鉄道 なぜ奥羽本線は福島から分かれているか 第三章 軍港と短距離路線 なぜ横須賀線はトンネルが多いか 第四章 陸軍用地と都心延伸 なぜ中央線は御料地を通ることができたか 第五章 日清戦争と山陽鉄道 なぜ山陽本線に急勾配の難所があるか 第六章 日露戦争と仮線路 なぜ九州の巨大駅は幻と消えたか 第七章 鉄道聯隊と演習線 なぜ新京成線は曲がりくねっているか 第八章 総力戦と鉄道構想 なぜ弾丸列車は新幹線として蘇ったか 個人的な関心の度合いから、私が読んだのは、5→2→6→4→8→1→3→7章の順だ。しかし、前述した「明治時代から太平洋戦争の時代までの、外敵への恐怖感」を順序立てて理解していくには、やはり第一章から読んでいくのが妥当である。 「はじめに」で、陸軍の関与が最も強かったのは明治25年(1892年)頃の日清戦争開戦直前のころだと書いている。第一章では明治21年(1888年)に陸軍参謀本部が『鉄道論』という書物を刊行している。以降、日露戦争や太平洋戦争時の日本軍が鉄道のことをどう捉えていたかが描写される。私のようにランダムに読むとその時系列が崩れてしまい、結局、通しで読み直すことになる。 * * *
そういう点では本書の本質ではないのだけれど、真っ先に第五章「日清戦争と山陽鉄道」を読んだのは、山陽本線(山陽鉄道)の山口県のルートどりの地図があったからだ。かねてより、山口市があのような位置にあるためか山陽本線は素通りしていることと、なぜ防府から山口に抜けなかったのかということに疑問を感じていた。それが、複数のルート案とともに解説してあるから真っ先に読んだのだ。 その地図と本文を読むと、「六日市」「日原」とたどるルート案があったことがわかる。ここからは憶測だが、「岩日線(いまの錦川清流鉄道)」は、このルートの一部をたどる。このルートが鉄道敷設法別表に載ったのは、このときの計画というか空気が残っていたからではないか。それが延々残り、「岩日線」として建設されたのではないか。結局は、錦町以北は工事が凍結されたので、六日市~日原間は2回も鉄道に振られてしまったのではないか。最後は憶測だが、その「物語性」はなかなかのものだと思う。 * * *
本書は主として「ルート決定」の観点でまとめられたものである。続編として「運営」の面ではどうだったのかを望みたい。国鉄(組織は行政上、随時変わっている)や車輌製造会社、製鉄会社がどう考えてどう動き、軍隊と戦争にどう影響を及ぼしてきたのか。大量の蒸気機関車や貨車が外地に送られ、ほとんどすべてが戻ってこなかったのは鉄道ファンが広く知るところだが、その意思決定のプロセスはどうだったのか。車輌製造会社において市場としての外地はどうだったのか。「地図ファン」が読者層と思われる本書とは読者の数の桁が違う(少ない)かな。  こういうおもしろさがある。国鉄総裁だった藤井松太郎という人物がいる。東海道新幹線の計画に反対して技師長を追われ、後に考えを改めて島秀雄の後に再び技師長に就任し、のちに国鉄総裁となり、労働問題で職を追われた土木技術者だ。その藤井松太郎の評伝『剛毅木訥』(田村喜子)に、藤井が「陸軍省第一鉄道部附」として「鉄道省派遣橋梁修理班作業隊長」として中国に派遣され、作業する様子が描かれている。小説仕立ではあるが、本人に細かな取材をしているものなので、その様子がよくわかるとともに、鉄道連隊との関係も書かれている。藤井は、大河も大河である淮河に架けられていた9連の200フィートトラス橋のうち7連が人為的に破壊され、水中に没していたのを引き上げ、修復する。現地には、偶然、藤井の鉄道省1年後輩の篠原武司(のちの鉄道技術研究所所長、鉄道建設公団総裁)が鉄道連隊の少尉として、中隊長として現地にいた。そうした、官と軍の関係を整理して理解してみたい。 * * *
最後に、本書の記述はすべて元号が基本となっている。これは感覚的な把握にとてもいい。私が高校生のときには、日清・日露・第一次大戦は、1894・1904・1914年と10年おきだ、と教えられた。でもこれではその背景の時代を感じられない。1894年は「まだ」明治27年で国内も安定していない、1904年は「まだ」明治37年、1914年に至ってようやく大正3年、重工業の国産化が進んでいた時期だ。鉄道史も、西暦ではなく元号で考えると、まったく違う見え方をしてくると思う。「明治維新からたった○○年で!」というように。もちろん、本書の元号も、そういう把握を意図しているだろう。そういう配慮が行き届いた本だ。 |
カレンダー
最新記事
(04/12)
(04/02)
(02/15)
(01/01)
(12/31)
(11/20)
(11/11)
(11/05)
(10/26)
(10/25)
カテゴリー
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
since 2010.7.30
アクセス解析
フリーエリア
|





