プロモーション
カレンダー
最新記事
(02/10)
(04/12)
(04/02)
(02/15)
(01/01)
(12/31)
(11/20)
(11/11)
(11/05)
(10/26)
カテゴリー
twitter2
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
since 2010.7.30
アクセス解析
フリーエリア
プロモーション
プロモーション
No Image
男鹿半島北部の板塀の風景
西山の潮風よけのような、海べりの、板塀で囲われた道路風景が好きだ。母方の実家があった柏崎の海岸部も、そんな風景だったし、その家もそうだった(いまは、ほとんどない;下記の家がその家という意味ではない)。
秋田県の男鹿半島北部の海べりに、すてきな風景があった。


左の、2階の半ばに届こうかという高い塀は住宅を囲うもの。右の低い塀は、畑を守るもの。


この板塀が、風化し、乱杭のようになっていると、ああ、浜辺だ、と感じる。
秋田県の男鹿半島北部の海べりに、すてきな風景があった。


左の、2階の半ばに届こうかという高い塀は住宅を囲うもの。右の低い塀は、畑を守るもの。


この板塀が、風化し、乱杭のようになっていると、ああ、浜辺だ、と感じる。
- 0 コメント
- 2019/05/18 20:00
No Image
央橋(なかはし)

「央橋」と書いて「なかはし」と読む。常陸太田の国道の旧道が渡っている。

南側。ウェブとリブで塗り分けられている。
コンクリートの色に似つかわしい雲の色。この日から晴れが5日続くという予報だったのでバイクで出たのだが、この後、一瞬、土砂降りになり、カッパを着る間にびしょ濡れになってしまった。

南側。


親柱は右書きで、左に「央橋」、右に「里川」。親柱から飛び出した意匠は、見た目の安定化を出すためか。

北側。


親柱、左は「なかはし」、右は「昭和十二年十一月竣功」。
説明看板によれば、地元では「めがね橋」と呼ばれているとのことだが、ほんとかな。2連の上路アーチが水面に映ると、二つの円が並ぶ(「○○」となる)から「めがね橋」と呼ぶんじゃないのか。
- 0 コメント
- 2019/05/16 20:00
No Image
佐渡汽船 さど丸

(以下、1981~1983年ころの情景としてお読みください)
佐渡は、毎日のように「裏の浜」で見えていた。当然、佐渡汽船も常に視界の中にいた。佐渡汽船のりばまで徒歩圏内(隣の校区)だったし、信濃川べりはよく行っていた。
ぼくが子供の頃は、佐渡汽船はさまざまな大きさのフェリーを運航しており、たしか大きな船は「おとめ丸」と「こがね丸」、そして小学校6年生のときには大きな「こさど丸」が就航した。当時直江津航路にいた「おおさど丸」より「こさど丸」のほうが大きいのは、なんだかファニィな感じがした。
そんな中、もっとも好きなのは、ちんまりした「さど丸」だった。大型の「おとめ丸」「こがね丸」に対して、こんな小さな船も混ざるのか。東京の電車で例えて言えば、10両編成の電車が行き交うのに、なぜか当該列車だけ4両編成、みたいな感じか。京急か。

その「さど丸」は、確かヨコに「新潟-赤泊」と書いてあった気がする。もう佐渡航路には入っていなかったような。あくまでも記憶ですが。その「さど丸」も、いつしか新潟港から姿を消した。寺泊~赤泊の両泊航路に転配されたのだ。以降、ぼくもあまり気にかけなくなった。

その「さど丸」の模型が、佐渡汽船ターミナルで展示されていたので見に行った。11月末まで転じされている。

総トン数599.7トンというが、のちに1200トン級に改造されている。といっても計算方法というか、甲板の考え方の変更なのか。

佐渡汽船初のカーフェリー。

この公式写真は、小学校6年生のときの佐渡への修学旅行の際にもらった佐渡汽船のパンフレットの裏にも載っていた。

「ときわ丸」の模型と「ときわ丸」。
●「さど丸」に関するサイト
・インドネシアで現役の「さど丸」の写真
https://journals.worldnomads.com/merantau/photo/11011/870089/Indonesia/Ferry-heading-to-Padangbai-from-Lembar
・「さど丸」を含む各船舶の「その後」
【船】佐渡汽船のフェリー達(2016/9/14追記)
●関連項目
・佐渡汽船 ときわ丸 車輌甲板のディテール
・佐渡汽船 おとめ丸のディテール
- 0 コメント
- 2019/05/14 20:00
No Image
羽越本線 三跨川橋梁

新潟県の国道7号を、新発田方面から村上方面に向かうと、岩船町駅の手前で左にコンクリートアーチが見えてくる。これが三跨川橋梁だ。読み方は「さんこがわ」。国土地理院の地形図では「百川」となっている。

一瞬、新たな時代のコンクリートローゼか…と思うが、桁が太い。ライズはかなり低い。

桁と補剛アーチの太さの違いがわかる角度。
竣功は2007年12月。いつの撮影かはわからないが、国土地理院の空中写真(「2004-」または「最新」)において、工事中の姿を見ることができる。下記写真のピンは現在の橋梁の位置。マッピングが1mほどズレている。

(カシミール3Dで地理院地図を表示)
これを見ると、架け替えの際、線路をいったん下流側(左)に移設し、架け替えてから仮設線を撤去しているようだ。現地に行っても、その痕跡はわからないほど。
この橋梁についての論文
・長大PCランガー橋の設計と施工--JR羽越本線 三跨川橋りょう(皆川 一四,吉田 昭二,一場 浩一 他)
施工会社のサイト
・安部日鋼工業
・第一建設工業
- 0 コメント
- 2019/05/13 20:00
No Image
新屋敷架道橋
『東京人』2017年11月号に、鉄製橋脚の記事を書いたが、そこでは採り上げなかったのが、中央・総武線の千駄ヶ谷~代々木間にある新屋敷架道橋。強いて言えば、これはラーメン構造なので…というところだが、実際は、ここだけ飛び地のように存在しているので採り上げなかった。
さて、その新屋敷架道橋。またいでいるのは明治通り。

中央径間がπの字に、側径間は橋台と中央径間にのっかっている(カンチレバー)。

カンチレバーの接合部。橋脚は、補強的に覆われているようにも見えるが、リベットだし、後付けではないようだ。

スキューしているので、どこを正面として撮るか、なかなか決めづらい。4線あり、橋脚は左2線、右2線が剛結されている。桁の間もプレートで覆われているが、バラストがあるわけではない。

橋脚の基部。ピンで受けている。
『東京人』11月号「高架下の誘惑」にて、錚々たる方々の中におじゃまして、おこがましくも鋼製橋脚図鑑を書きました。ぜひご覧ください。その直前に、petiskaさんにブレースについてご教示いただいたのがすごいタイミングでした。ありがとうございました。 pic.twitter.com/JcP300A6fT
— 磯部祥行 (@tenereisobe) 2017年10月3日
さて、その新屋敷架道橋。またいでいるのは明治通り。

中央径間がπの字に、側径間は橋台と中央径間にのっかっている(カンチレバー)。

カンチレバーの接合部。橋脚は、補強的に覆われているようにも見えるが、リベットだし、後付けではないようだ。

スキューしているので、どこを正面として撮るか、なかなか決めづらい。4線あり、橋脚は左2線、右2線が剛結されている。桁の間もプレートで覆われているが、バラストがあるわけではない。

橋脚の基部。ピンで受けている。
- 0 コメント
- 2019/04/21 20:00
No Image
『凹凸を楽しむ 阪神・淡路島「高低差」地形散歩』(新之介著)

新之介著さんの、シリーズ3冊目となる『凹凸を楽しむ 阪神・淡路島「高低差」地形散歩』が刊行された。今回の目玉は「淡路島」だ。ぼくはそう思っている。
淡路島は、何度か「通ったことがある」が、きちんと全島を回ったことはない。ただ、えぬ氏の案内のもと、南東の海岸沿いを訪ねたことがあり、もっと淡路島のことをよく知りたいと思っていたところに本書が出た。
【関連記事】
石垣の集落

本書の章立てとして、第一部「高低差概論」の3章のうち1章が淡路島。第二部「高低差を歩く 地形視点で町を眺める」の15項のうち4項が淡路島。つまり、全体の3割ほどが淡路島に割かれているので、第一部を通読後、第二部は淡路島から読み始めた。
地形と地質について、すごく大雑把に教えてくれるものはなかなかなく、Wikipediaですらそういうふうには書かれていない。しかし、本書ではズバリ「淡路島の地形と地質は、北部と南部で大きく異なる」と書かれ、それぞれの説明がなされ、こういうことに関心を持つ人が興味を持ちそうな話題を散りばめていく。地質などは素人にはなかなか理解しづらい(覚えづらい)ことだが、それを、興味が向くよう(現地に行きたくなるよう)書かれている。
沼島の項では、こうだ。「島の北側と南側では地質構造や岩石の種類が大きく異なる」。そこには「超希少な黒崎の鞘型褶曲」等々。
通常、高低差本では地形の利用の妙味がメインであり、地質についてはあまり触れないことが多い。高校の授業としてほぼ「地学」がないために基礎知識すらない人が多いために「わかならい」と関心を示さない人が多い(=売れる要素とならない、むしろ逆)と思っているが、地質についていろいろ書いてあっても、それがスッと入ってくる、そこに行ってみたくなる構成になっている。
また、淡路島というと、つい「島」のことが書いてあるかと思いきや、言われてみれば当然なのだが、鳴門の渦潮もまた深く淡路島に関係していて、「淡路島単体」ではなく、「淡路島が果たす役割」「本州や四国との関係」についても多く言及されているのが、とてもおもしろい。紀淡海峡の要塞についてももちろん詳しく述べられている。

『凹凸を楽しむ 阪神・淡路島「高低差」地形散歩』のラストは、淡路島の三原平野の円筒分水群について書かれている。えぬ氏に、そこに連れて行っていただいたときのリンクを下記に示す。
【関連記事】
分流する用水路と円筒分水

今度は2~3日かけて回ってみたい。
- 0 コメント
- 2019/04/14 20:00
No Image
『「地図感覚」から都市を読み解く 新しい地図の読み方』(今和泉隆行)
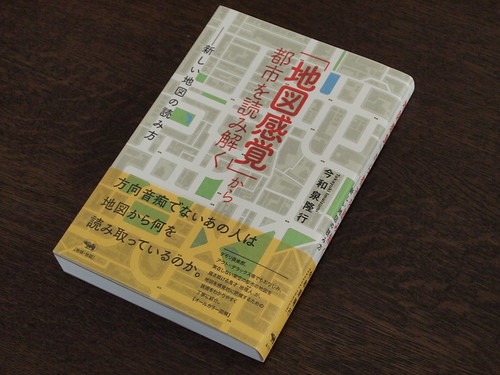
「地理人」こと今和泉隆行さんの新刊。「空想地図」の作者として著名な今和泉さんの、その空想地図のリアリティを支えるのがこの「地図感覚」だ。完全に架空の地図を見る人は、なぜそれに違和感を持たないのか。それを逆から説明し、「地図はこうなっているのだ」と解き明かして、いろいろな地図のスタイルを楽しむことができる作りとなっている。
この手の本として、とりわけ珍しいのは、昭文社の都市地図『街の達人』『シティマップル』から多数の図版を転載している点だ。年代、スケールによる地図表現の違いを比較するためには、同じ会社のシリーズを使うのがいちばんだ。そこには、地図表現の違いはもちろん、制作の理由も垣間見える。それについては後述する。
「地図感覚」とは、今和泉さんが定義した言葉で、「人々が潜在的に持っている地理感覚や土地勘、経験を地図で引き出して読み解く感覚」としている。スケールがわからない場面で自分なりのスケールを持てばすごく状況を把握しやすくなるよ、ということ。
ぼくは日常的に「1歩75cm」「線路は1本25m」「電車のホームは200m」などということを考えながら動いているが、並行して「徒歩なら1km11分」、「都心部、昼間のクルマ移動なら15km1時間」「郊外なら30km1時間」「バイパスなら40km1時間」「バイクでバイパスなら100km2時間」とか、そういうスケールもある。
また、面積で把握するというのもある。100m四方の土地なら、2万5000分の1地図では4mm四方もの大きさで描かれる。2万5000分の1地図で1mm四方では25m四方でいい。約190坪、持つには広いがそれくらいの土地を持つ人は多いだろう。かつてこんな記事を書いたことがある。
・雨竜町にある(あった)「十六万坪」地名
おもしろいと思ったのは、学校の校庭の比較。

学校の校庭というのは、空中写真や衛星画像ではとても目立つものだ。下記のGoogleMapsでところどころ茶色くハゲているのは校庭だ。都市部の小学校というのは一定の間隔で配置されているので、小学校の位置を把握していると、空中写真や衛星画像での地図の把握が容易になる。
上のだと「ラベル」こと物件名が表示されてしまうので、下記に消したものを画像として転載する。

これは新潟市の広域だが、「新潟島」ハゲ部分は、小中学校と高校である(「元」も含む)。いま気づいた、新潟高校は校庭広いな。
ズームアップする。

こうすると、いかに地図のハゲが目立つかわかると思う。
地理人さんの本にかこつけて、いつか書こうと思っていた、校庭の話を書いてしまった。
* * *
本題とは外れるが、作り手側から見た「地図表現」について。
地図出版物がデジタル化したのは90年代から2000年代で、昭文社は2000年代前半まで「従来製版」の地図も刊行していた。昭文社が全デジタル化に時間がかかったのは、一図一図ではなくて「全国をすべて描き、自由に切り出せる」形式で整えたから…かなと推測している。
私が仕事で関わっているところでは、1995年に一気にデジタルに切り替えた。それまでは、要素ごと(※)にそれぞれのフィルムに描き、重ねて撮影していた。製版の精度もいまとは比較にならないので、使う色数は少ない方がよかった(だからCMYKの単色や100%、50%同士の掛け合わせが多い)。それが1995年から一図一図をillustratorで起こしたものになった(※※)。そんな事情も比較で読み取れる。
昭文社のツーリングマップルは、「ツーリンツマップ」時代から愛用しているが、デジタル化した直後はとても見づらくなった。崖の表現や道路の側線があまりに細すぎるようになった。illustrator上では線はいくらでも細くできるが、印刷の限界は、私の感覚では0.12mm。それより補足するとかすれたグレーにしか見えない。そういう視覚を基準に補正していくことも、地図に限らず印刷媒体ではとても重要になる。
(※)道路の側線/載せる色ごと/建物(特建という)/岸線/河川や海の青/山の陰影(ボカシという。これは「絵」だ)/文字、等々。
(※※)もちろん制作費は莫大だ。A5判で一図10万くらいだった気がする。なにしろガイドブック40冊分の地図予算が1億2000万だ。(それを回収できるくらい売れる時代だったのだ)。
【関連項目】
『みんなの空想地図』(今和泉隆行著/白水社)
- 0 コメント
- 2019/04/06 20:00







