|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  北海道の「へそ」の辺縁部、しかしその中心部よりも金山ダムのほうが近い場所の国道沿いに、個性的な建物が並んでいる。いまはもう営業していなさそうな自転車屋を見ると、看板の上に、古いブリヂストンのマークが掲げられていた。  この、凸の中に「BS」と入っているマークは「キーストンマーク」と呼ばれ、「BRIDGESTONE」という文字列(「ブリヂストンシンボル」。現在は「ブリヂストンロゴ」という)とは異なる扱いがなされる。この、ゴシックの「BS」は、創業当時から2回目のリファインがなされた1974年以降のもの。すなわち、この看板が作られたのは、1974年以降ということになる。意外に新しい、と感じないだろうか。 「キーストン」とは、要石。構造としてのアーチの最上部に上からはめ込むことで、アーチが完成するもの。トンネルや橋梁で、表面に出るキーストンだけ石だったりするなど、シンボルになりやすいものだ。これがキーストンを模したものだと知るまで、私はバルブかなにかだと思っていた。 PR
十勝港での石炭荷役。船はST PINOT。
 かつて近海郵船が寄港していた十勝港。まさにそこに係留され、荷役中。写真左の黄色い屋根が、当時の待合所。  大きなデリックが4基。  船倉からつかみ上げられた石炭が、ドジャーッと、けっこうな高さから落とされる。  これは、前から3基目のデリック。こちらはバケットが2連になっている。その下では、ホイールローダーが、石炭を整地(?)中。   十勝港ターミナルは立ち入り禁止だが、いまも業務用施設として使われているようだ。  近海郵船の東京ー釧路航路最後の1999年夏、釧路からブルーゼファーに乗った。左がスーパーテネレ、2012年夏のミッショントラブルで廃車して、いまも家にある。右は、いまウチで動く唯一のランツァ、それも今年、クランクベアリングが逝ってしまい、いま修理の検討中。 この航路は片道30時間。行きは2泊、帰りが1泊、それを2隻で回していたので、3日に2便という航路だった。1996年から、集客、というか十勝発の荷を積むため、十勝港に寄るようになった。このときも、十勝港に寄ったのは憶えている。それでも業績は好転せず、1999年秋に撤退した。 東京ー釧路に乗ったのは、1995年と1999年の2回、それも釧路発のみだったと思うが、1998年も乗ったかもしれない。記憶がないし、メモもない。  新日本海フェリーの「ゆうかり」は、1階甲板に通じる前後のランプウェイのほか、2階に直接出入りできるサイドのゲートがある。ここには港側から可動橋が延びている。その出入り口を、内側から見る機会があった。場所は新潟港。  このゲートは、プラグドアのように、まずいったん外側に出た後、前方にスライドしていく。この時点では、港側の可動橋の位置は、そのままではつなげられない程度にずれていた。  ゴゴゴゴゴゴ…とスライドしていき、完全に開いた後、可動橋が動き始める。まず、船内から向かって右にずれていた(という表現が適切かはわからない)可動橋が左に水平移動する。そして高さを調節し、上に巻き上げられている渡り板部分を繰り出す。その際、渡り板の裏の桟に溜まっていた雨水がザザザとしたたり落ちていった。 そして無事に可動橋が渡されると、下船開始となる。  富良野市のはずれのはずれ、国道沿いに商店が並ぶがどれも閉めて長いことになるような地区に、ワム60000の廃車体があった。倉庫として使われているのだろう。ただ、傾いている。 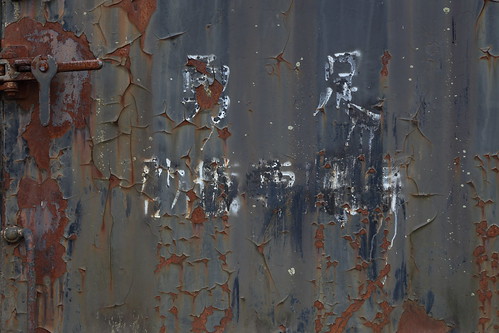 「勇足」。勇足駅といえば、池北線の駅だ。ずいぶん遠くから持ってきたものだ。その下の文字は、ちょっと読めない。「砂積専用車」?  そういえば、廃車体は焼却炉が傍らにあることが多い気がする。 ●2018.9.17追記 RasandRoadさんから「砂糖専用車ではないか。北海道糖業本別製糖所への引込線があったようだ」というご指摘をいただきました。たしかに「砂糖」に見えますね。
 沙流川本流に位置する岩知志ダム。先の「送水橋」「余水橋」と水圧管路の水はここで取水されている。撮影地点は国道237号の橋。  下流側を見る。沙流川が、谷を深く刻んできたのがわかる。  両側を見ることができる橋の名称は「景勝橋」。ダムビューも「景勝」である。岩知志ダム稼働よりも国道開通のほうが早いと思われるので、付け替え道路だと思うが、果たして。 |
カレンダー
最新記事
(04/12)
(04/02)
(02/15)
(01/01)
(12/31)
(11/20)
(11/11)
(11/05)
(10/26)
(10/25)
カテゴリー
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
since 2010.7.30
アクセス解析
フリーエリア
|



